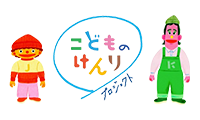夢は大きく:少数民族の女の子たちも学校へ
<ラオス>
<2004年1月14日掲載>
パンヤは、いつも先生たちに、夢は大きく持つようにと言われています。「学校に行くのってすごく楽しいわ」と11歳のパンヤは言います。「結婚なんてしたくない。いっぱい、いっぱい勉強して、大学に行って、会社で働いて…できればお医者さんになりたいな」
シェーンクアン県のモン族の女の子にとって、こうした夢は見果てぬ夢かもしれません。何しろこの地域の子どもたち(特に女の子)は、学校にも行けない子が多いのですから。でも、ノンペット中等学校の場合は、少し状況が違います。18歳になるポンサメイは、これから大学を受験しようとしているたくさんの女の子のうちのひとりです。「できれば医学方面に進みたいと思っているんです」
ラオス人民民主共和国の少数民族の女の子がなかなか教育を受けられない原因はいろいろあります。少数民族が住む農村部には学校が少なく、先生の数も少ない。長い距離を学校まで歩かせたくないという娘を思う親心。教育は男の子のものだという考え方。家事の担い手として重宝がられる女の子。そして、女の子によっては、早い結婚(ときには12歳で)のため、学校を途中であきらめなければならない子もいます。
「ジェンダー(性差)のギャップ」を埋める
こうした理由から、ユニセフは特に農村部で、教育の質を高める努力を続けており、教育当局と協力し合ってすべての子ども(特に女の子)に教育の機会を提供するために、親の説得にあたっています。
「この地域では、教育に対する考え方が一変しました」とポンサメイは言います。彼女の親は13人の子ども全員を学校に通わせました。教育当局者が村にきて、知識や技術が貧困の悪循環を終わらすことができるのだ、と説明したそうです。「村人は、子どもたちにもっといい生活をしてほしいと思っているんです」
「どうして女の子だけが損をしないといけないの?」とパンヤ。「私たちだって男の子と同じように知識を得て、家族を助けることができるはずよ」彼女の村では、すでに「ジェンダー(性差による)ギャップ」は過去の遺物となりました。「教育の価値はあっという間に知れわたりました。まわりが子どもたちを学校にやるようになると、みんながそれに追随します」と、パンヤの先生であるスリチャン先生が説明してくれました。「でも、教育の質も良くないとだめです。学校に行く価値がなければ、家族だってどうでもいいと思いますから。ユニセフのおかげで、資金面でも助かっていますし、教師への支援もあります。教師向けの研修もあるんですよ。コミュニティを巻き込みながら、学校の施設を改善する方法も学びました」
すべてのコミュニティがこのように物分りがいいわけではありません。隣の地区のノン・ナム村には2つの小学校があります。シー(10歳)は、どちらの学校にも近いところに住んでいますが、読み書きができません。学校に行っているの?と聞くと、彼女は涙を浮かべながら答えました。「行けないの。お父さん、お母さんがダメだっていうから」
「教育が大切なのは分かっています」とシーのお母さん。「でも、家でやらなければならないことが山ほどあるんです。私たちは貧乏ですから、ほかに選択の余地はありません」地元の学校の質があまりよくないのも、学校に行かせたくない要因のひとつです。ノン・ナム村はユニセフの支援を受けていません。教師の多くは研修も受けていませんし、学校に行っていない子も多いのです。
再びノンペット村。ポンサメイは野菜畑の草とりをし、薪を割ってから宿題にとりかかります。「子どもたちを学校に通わせるように親たちを説得し、学校もみんなに平等の機会を提供できるようになれば、すべての親が娘を学校にやると思うわ」とポンサメイは言います。
ポンサメイのコミュニティは、ほかの村々に比べて確かに意識が高いといえます。しかし、パンヤの村もそれを見習い始めたことを考えると、成功例が広がることで、やがてはそれが「ふつうのこと」になるでしょう。パンヤは学校に行く前に水汲みに出かけ、家族のために朝食も作ります。「ときどき、雑用がたくさんありすぎて、学校に遅れることもある。それで先生たちが怒り出すこともあるわ。でも、それはちょっとの間だけ。宿題は必ずやっていくから、許してもらえるのよ」 …必ず? と先生に目配せすると、先生は「いつもとは限りませんが、一生懸命やっていることだけは確かですから」と優しく微笑みました。
2004年1月
ユニセフ・ラオス

|トップページへ|コーナートップへ戻る|先頭に戻る|
 寄付方法のご案内
寄付方法のご案内
 ご寄付による支援例・成果
ご寄付による支援例・成果
 領収書
領収書
 その他のご協力方法
その他のご協力方法
 個人のみなさま
個人のみなさま
 学校・園のみなさま
学校・園のみなさま
 大学生ボランティア
大学生ボランティア